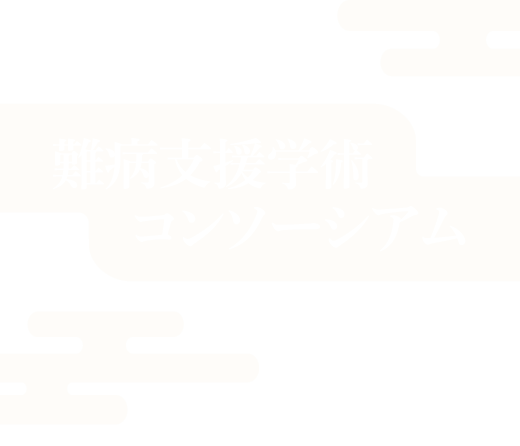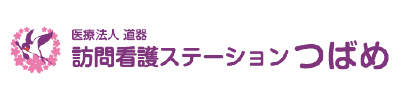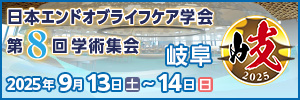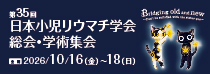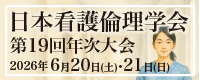日程表・プログラム
プログラム
大会長講演
大会長講演1(第13回日本難病医療ネットワーク学会学術集会)
ALSへの挑戦~つながりに支えられた34年間~
- 座長
- 青木 正志(東北大学大学院医学系研究科)
- 演者
- 漆谷 真(滋賀医科大学)
大会長講演2(第11回神経難病リハビリテーション研究会)
神経難病リハビリテーションの進め方
- 座長
- 花山 耕三(川崎医科大学)
- 演者
- 中馬 孝容(滋賀県立総合病院)
大会長講演3(第30回日本難病看護学会学術集会)
多職種連携における難病看護の専門性ー第30回の節目に問うー
- 座長
- 須坂 洋子(獨協医科大学)
- 演者
- 布谷 麻耶(武庫川女子大学)
特別講演
難病患者の総合的地域支援に繋がるコンソーシアムの役割
- 座長
- 望月 秀樹(大阪大学大学院医学系研究科)
- 演者
- 小森 哲夫(東京医療保健大学 / 多摩リハビリテーション病院)
基調講演
難病支援学術コンソーシアムで何がしたいか、何ができるか。
- 座長
- 大窪 隆一(藤元総合病院)
- 演者
- 望月 秀樹(大阪大学大学院医学系研究科)
シンポジウム
シンポジウム1 遠隔医療とIT
【シンポジウムのねらい】
診療報酬改定により遠隔診療に保険算定が認められた。遠隔医療は、特に運動機能障害を伴う神経難病患者にとって非常に有用なはずである。IT技術は進歩し、遠隔診療への参入を狙う企業も出てきていますが、実際には思うほど普及していない現状がある。このシンポジウムでは、遠隔診療で対面診療の質を担保するための方法、遠隔診療に欠かせないデジタル技術の実際について、識者や経験者の先生方からお話を伺い、課題を共有することで、実行可能な遠隔診療の姿について考える場になればと期待する。
- 座長
- 矢部 一郎(北海道大学)
- 演者
- 高橋 宜盟(一般社団法人結ライフコミュニケーション研究所)
- 演者
- 宮﨑 雄生(国立病院機構北海道医療センター)
- 演者
- 波田野 琢(順天堂大学)
シンポジウム2 大学病院・拠点病院がつなぐ病診多職種連携のこころみ
【シンポジウムのねらい】
「住み慣れた地域で、最適の治療を受ける」という理想を掲げる難病法では、連携拠点病院を頂点として、分野別拠点病院、協力病院、かかりつけ医の綿密で効果的な連携が求められている。そして、連携拠点は多数の診療科にまたがる難病に対応できるよう、大学病院や地域の基幹病院が担当することが多いと思われる。こうした施設は急性期病院のため、診断後は分野別拠点病院や地域病院に逆紹介し、専門的なフォローアップがなされていない現状が懸念されている。このシンポジウムでは、難病の診断、大学病院や急性期の基幹病院が地域の診断と治療方針を決定した後に、地域難病医療ネットワークにおいてどのような役割を果たすべきであるのか、実例をご紹介いただきながら、考える機会を提供したい。
- 座長
- 太田 康之(山形大学大学院医学系研究科)
- 新井 香奈子(滋賀県立大学)
- 演者
- 平山 剛久(東邦大学)
- 演者
- 相澤 千草(滋賀医科大学医学部附属病院)
- 演者
- 蛯澤 直美(札幌医科大学附属病院)
シンポジウム3
難病リハビリテーションの取り組み(診断時から在宅までのかかわり)
【シンポジウムのねらい】
リハビリテーションは、病院でのリハビリテーションを行うだけでなく、在宅の現場においても必要なアプロ―チの一つとなっている。担当患者さんの生活やご家族も含めて検討しなくてはいけない場面は多いと考えられる。難病疾患と診断された時点から、リハビリテーションによる評価・指導が開始され、さらに、在宅の現場においても適切な評価指導等が行われることで、その患者さんのADL/QOLは維持・向上できると考えている。
- 座長
- 小林 庸子 (国立病院機構 箱根病院)
- 演者
- 浅川 孝司(国際医療福祉大学)
- 演者
- 高橋 香代子(北里大学)
- 演者
- 秦 若菜(北里大学)
シンポジウム4 難病療養者の治療と仕事の両立支援
【シンポジウムのねらい】
難病療養者が治療と仕事を両立するために、当事者である難病療養者、支援コーディネータ、専門職の立場からの報告を通して、必要な支援について検討する。
- 座長
- 伊藤 美千代(東京医療保健大学)
- 演者
- 藤井 滋生(彦根市立病院)
- 演者
- 中本 富美(医王病院)
- 演者
- 水野 光(関西医科大学)
シンポジウム5 難病医療の地域差をなくすには(先進県の試み)
【シンポジウムのねらい】
難病法施行後、各都道府県は独自の難病医療政策の立案や実施、拠点病院の配置と保健所を交えた地域の難病ネットワークを構築してきた。神経難病患者の多くは運動機能障害を有し、進行とともに移乗の介助、胃瘻や人工呼吸器などの医療処置が必要となり、家族の介護負担が徐々に増すことから、サポートにはマンパワーが求められ、必然的に24時間365日の対応が可能な事業所が必要となるが、その数は都市部に集中し、地域では利用が困難な現状が存在する。難病医療の地域差をなくすために各都道府県が行う試みを共有することは、全国レベルの地域差の解決に有効であると考える。このシンポジウムは(私が勝手に考える)難病先進県の試み、特に地域偏在をなくすための方策についてご紹介いただき、課題についてもご紹介いただくことで、他府県の難病医療従事者の課題認識と解決に向けての貴重な情報提供の機会となることを期待する。
- 座長
- 溝口 功一(城西クリニック)
- 演者
- 磯部 紀子(九州大学)
- 演者
- 漆谷 真(滋賀医科大学)
- 演者
- 今井 富裕(国立病院機構箱根病院)
シンポジウム6 小児成人移行体制の構築
【シンポジウムのねらい】
多職種の関わる難病患者の移行期医療において、医師、保健師、臨床保育士の立場からの実践報告を通して、どのような体制の構築が重要であるかについて検討する。
- 座長
- 望月 葉子(望月外科医院)
- 阪上 由美(大阪信愛学院大学)
- 演者
- 尾方 克久(国立病院機構東埼玉病院)
- 演者
- 三浦 雅子(かながわ移行期医療支援センター)
- 演者
- 髙野 祥子(福岡大学筑紫病院)
シンポジウム7 摂食と嚥下改善のための知恵
【シンポジウムのねらい】
神経難病の多くに嚥下障害が合併し、その改善は生命予後のみならずQOLも大きく改善するため、難病医療従事者の最大関心事の一つである。実際、嚥下障害の発見や評価方法、NST的な誤嚥対策から侵襲的な経管栄養、さらには誤嚥防止術まで、嚥下障害の理解と対策のために必要な情報が利用可能となってきたが、依然として現場では誤嚥性肺炎の合併は多く、誤嚥防止のための対策が不十分なまま、すぐに胃瘻造設を考慮することが日常茶飯事である。またALSや多系統萎縮症において、気管切開実施患者の経口摂取は誤嚥防止術によってより安全に実施が可能になるにもかかわらず、誤嚥防止術の知識が乏しいため、医師の先入観で初めから選択肢より除外する傾向がある。これは医療機関における耳鼻科医のスキルが大きく影響している現状がある。本シンポジウムの狙いは、嚥下障害に対して誤嚥性肺炎の予防と、QOLを保つための安全な経口摂取について、保存的に、内科的に、外科的に何ができるのかを実例について学びながら診療に生かす知恵を得ることである。
- 座長
- 野﨑 園子 (関西労災病院)
- 演者
- 平野 牧人 (近畿大学)
- 演者
- 落合 勇人 (新潟医療福祉大学)
- 演者
- 藤本 保志 (愛知医科大学)
シンポジウム8 希少難病にスポットを当てる!
【シンポジウムのねらい】
希少難病に焦点を当て、支援活動者や看護師、希少難病の当事者や家族からの報告を通して、希少難病への認知度を高めるとともに、必要な連携や支援について検討する。
- 座長
- 種村 智香(武庫川女子大学)
- 演者
- 西村 由希子(特定非営利活動法人ASrid)
- 演者
- 戸田 真里(京都光華女子大学 / 立命館大学)
- 演者
- 大塚 まどか(2型コラーゲン異常症患者・家族の会)
教育講演
教育講演1 コミュニケーションの総論と進歩
- 座長
- 成田 有吾(三重大学)
- 演者
- 井村 保(中部学院大学)
教育講演2 神経難病患者の呼吸機能評価と機器調整のHow to
- 座長
- 長野 清一(大阪大学大学院連合小児発達学研究科)
- 演者
- 寄本 恵輔(国立精神・神経医療研究センター)
教育講演3 難病医療制度のアップデート
- 座長
- 原口 道子(東京都医学総合研究所社会健康医学研究センター)
- 演者
- 山本 博之(厚生労働省 生活衛生局難病対策課)
教育講演4 新たな社会参加:eスポーツ
- 座長
- 田中 勇次郎(東京都作業療法士会)
- 演者
- 植田 友貴(西九州大学)
教育講演5 難病医療における遺伝のケア ー患者・家族の傍らで支援する皆様へのメッセージー
- 座長
- 柊中 智恵子(熊本大学)
- 演者
- 関屋 智子(金沢大学附属病院)
教育講演6 難病患者への臨床心理アプローチの在り方
- 座長
- 中山 優季(東京都医学総合研究所)
- 演者
- 鎌田 依里(東京福祉大学・大学院)
難病医療最前線
難病医療最前線1 薬物治療
【セッションのねらい】
神経難病の病態解明と新規治療開発は目覚ましい勢いで進んでいるが、本セッションでは、筋強直性ジストロフィー、家族性アミロイドポリニューロパチー、筋萎縮性側索硬化症の最新治療の開発現状について、エキスパートより解説いただく。さらに欧米で開発の進む新薬の治験の場として、日本がしばしばスキップされる現状をいかに解決すべきかについても学んでいただきたい。
- 座長
- 冨山 誠彦(弘前大学)
- 髙嶋 博(鹿児島大学脳神経内科)
- 演者
- 狩野 修(東邦大学医学部)
- 演者
- 中森 雅之(山口大学)
- 演者
- 関島 良樹(信州大学)
難病医療最前線2 難病の訪問看護の最前線
【セッションのねらい】
在宅で療養する難病患者が多い現状において、訪問看護の最前線ではどのような看護がなされているのかについて、ご経験にもとづき講演いただくことで、最前線の現状を参加者で共有し、よりよい看護に向けてどのような取り組みが必要か考える機会とする。
- 座長
- 冨安 眞理(静岡県立大学)
- 演者
- 畑中 文恵(兵庫県看護協会 尼崎訪問看護ステーション)
- 演者
- 雪田 昇一(ほ~むおんナースステーション)
難病医療最前線3 リハビリテーション・制度
【セッションのねらい】
リハビリテーション治療は難病患者への治療の一つであり、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病等、代表的な難病疾患を中心に、最先端のリハビリテーション治療についてご講演いただくことにした。リハビリテーション治療の可能性について学びの機会になると考える。
- 座長
- 植木 美乃(名古屋市立大学)
- 演者
- 山川 勇(滋賀医科大学)
- 演者
- 菊地 豊(公益財団法人脳血管研究所美原記念病院)
- 演者
- 植木 美乃(名古屋市立大学)
「学んで事例を考える」難病医療リレー
①炎症性腸疾患患者への意思決定支援
【セッションのねらい】
炎症性腸疾患患者の療養上の意思決定支援について、講演の後、事例を通して討議・意見交換することで、保健医療関係者が具体的な意思決定支援の在り方を学び、考える機会になる。難病患者と家族にとっては、主体的に療養上の意思決定に取り組む意欲を高めることができ、医療者とのコミュニケーションの重要性に気づき、相談方法を知る機会になる。
- 座長
- 山本 孝治(日本赤十字九州国際看護大学)
- 布谷 麻耶(武庫川女子大学)
- 講師
- 高津 典孝(福岡大学筑紫病院)
- 事例提示
- 阪上 佳誉子(インフュージョンクリニック)
- 事例提示
- 乾 彰弘(兵庫医科大学病院)
②難病診療における医療倫理の難しさ
【セッションのねらい】
神経難病は進行とともに、運動機能や認知機能の障害によって就労の継続性や日常生活の自立性が失われる疾患が多い。治療はいまだ対症的で非薬物治療やケアが中心となる。さらに核家族化と、高齢化による介護力の低下は医療処置の選択において意思決定が困難な状況を生む。本シンポジウムでは、合併症のために意思決定支援に難渋した事例を通じて、患者の希望に沿う最善策とは何かについて、様々な立場から考えていただく機会としたい。
- 座長
- 下畑 享良(岐阜大学大学院医学系研究科)
- 荻野 美恵子(国際医療福祉大学医学部)
- 講師
- 岩木 三保(九州大学大学院医学研究院保健学部門)
- 事例提示
- 髙田 久美子(滋賀医科大学医学部附属病院)
神経難病リハビリテーション研究会
リハビリテーションハンズオンセミナー
共催:滋賀県理学療法士会 ※事前申込制(参加登録と合わせてご登録ください)
①呼吸リハビリテーション1(徒手による呼吸リハビリテーション)
- 講師
- 菊地 豊(公益財団法人脳血管研究所美原記念病院)
- 上出 直人(北里大学)
②呼吸リハビリテーション2(排痰・気道クリアランス)
- 講師
- 三浦 利彦(NHO北海道医療センター)
- 宮川 哲夫(高知リハビリテーション専門職大学)
③摂食嚥下リハビリテーション
- 講師
- 秦 若菜(北里大学)
- 小森 規代(国際医療福祉大学)
市民公開講座&多職種交流会
自助・共助・公助のつながりが支える神経難病患者の災害対策
- 座長
- 宮地 隆史(国立病院機構柳井医療センター)
- 今福 恵子(豊橋創造大学)
- 演者
- 林 秀樹(岐阜薬科大学)
- 演者
- 中根 俊成(富山大学)
- 演者
- 北野 晃祐(村上華林堂病院)
コミュニケーションワークショップ
ICT機器のアクセシビリティ機能とコミュニケーション支援機器の活用
- 座長
- 井村 保(中部学院大学)
- 講師
- 小林 大作(株式会社アシテック・オコ 代表取締役)
コーディネーター教育コース
遺伝性難病の患者と家族への対応
- 座長
- 川田 明広(康明会病院)
- 関本 聖子(東北大学病院地域医療連携センター)
- 講師
- 須坂 洋子(獨協医科大学)
- 事例提示
- 須山 和子(公益財団法人ヘルスサイエンスセンター島根)